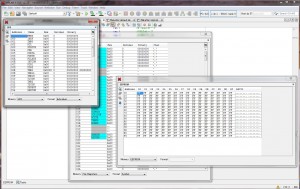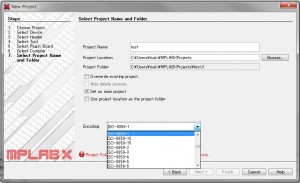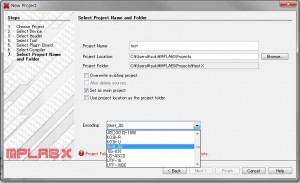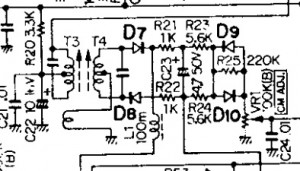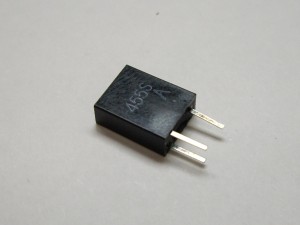今更であるが、数式を使わないでを記載してみた
当たり前のことの復習記事なので、殆どの方々はパスして下さい…である
SSBとはLSBまたはUSBどちらかを使った変調のことである
LSBとはキャリア周波数から下側の側波帯のことである
USBとはキャリア周波数から上側の側波帯のことである
この辺りのことは、ネットや、無線技術の教科書に詳しく解説がしてある しかし眠気を誘うのも事実であろう…..実際私がそうである
例えば、そこら辺のHF無線機で3.925MHzを受信してみて欲しい
この周波数はラジオ日経の第1放送である
<そこら辺のHF無線機で3.925MHz USBを受信している所>
殆どのデジタル表示の無線機であれば3.925MHzに合わせるだけで、受信モードがLSB、USBどちらでも、音声としては復調出来るハズである
モードを逆に切り替えても、音声として復調出来るハズである
アナログVFO機であっても、キャリアの0ビート付近で音声を復調出来るハズである
アナログ機の場合、LSBで完全に同調してあればUSBに切り替えて約2.6KHzずらすことで、音声を復調出来るハズである
<DRAKE R-4Aで3.925MHz LSBを受信している所>
これらの操作はキャリア周波数を中心として、それぞれの側波帯を受信した操作である
AM変調は、LSB信号とUSB信号それぞれの成分を持っているので、原則としてLSBとUSBどちらでも復調出来るのである
(例外は、LSBまたはUSB信号にキャリアを加えたAMモドキの信号)
しかし、LSBの信号をUSBで受信すると、モガモガ状態となって音声とはならない、逆もそうである
では、800Hzの一定信号をマイク端子から入力してLSBで送信してみる
これは単なるキャリア信号で、表示周波数から800Hzを引いた周波数のCWである
では、800Hzの一定信号をマイク端子から入力してUSBで送信してみる
これも単なるキャリア信号で、表示周波数から800Hzを足した周波数のCWである
音声信号は帯域約2.6KHz(殆どのフィルタの場合)の様々な周波数成分の寄せ集めと考えることが出来る
USBとUSBの違いのポイントは音声スベクトラムの高低が逆である点である
この辺りは、RC発信器の出力をマイクに入力して、色々と実験してみると楽しい
当然、出力はダミーロードである